※この記事は、執筆者が研修医の時に作成した記事です。
日本人の主な死に方
思考を再開しましょう。あなたは死について真剣に考えたことがありますか?
概念としての死ではなくて、もっと生々しいもの、たとえばあなた自身や、あなたの親が死ぬことについて、という話です。それはいつ、どんな風に訪れるでしょうか? それはどのくらい苦しいでしょうか? 死に至るまでの1カ月間、あるいは1年間、あなたはどのように過ごしているでしょうか?
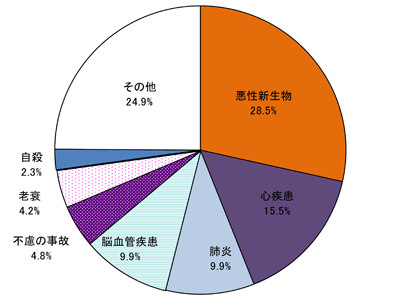
(主な死因別死亡数の割合(平成23年) 平成23年人口動態統計より)
お示しした図は、平成23年度における日本人の死因の割合です。
第1位が癌などの「悪性新生物」、第2位が心筋梗塞に代表される「心疾患」、第3位と第4位が僅差で「肺炎」と「脳血管疾患」という具合です。事故や自殺でない限り、我々はだいたいこのどれかで死にます。
第1位の「悪性新生物」について、少し具体的に想像してみましょう。
たとえば「悪性新生物」の多くを占める「肺がん」で死ぬとします。
肺がんと診断されたあなたは、まず手術をするか、化学療法をするかの選択をしなければなりません。手術をすれば根治の可能性がありますし、少なくともその後しばらくはがんに煩わされずにすみます。しかしながら、一定の確率で再発することになりますし、そもそもすでに浸潤、転移が進んでいて手術ができないこともあります。この場合は化学療法を選択することになります。
化学療法にはアルゴリズムがあって、年齢やがんの組織学的な種類によって、最初に使うべき薬が決められます。それがうまく効かなかったり、重い副作用が出てしまった場合には次の薬を試します。
副作用というのは軽いものから重いものまでさまざまです。食欲が落ちたり吐き気を催したりするのは軽いほうで、場合によっては白血球が少なくなって重篤な感染を生じたり、血小板が少なくなって消化管から血が出たりします。吐き気程度なら治療を続けますが、重い副作用が出ると薬をやめなければいけません。そうやっていくつかの薬を試しながら、だんだん病気が進んでいくわけです。
ステージによっても異なりますが、肺がんの5年生存率(診断されてから、十分な治療を行ったうえで5年間生存できる確率)は25%程度。数字上はつまり、4分の3の確率で5年以内に死ぬことになります。
肺がんであれば、骨に転移すれば早くから痛みが出たり、脳に転移すれば神経症状が出たりしますが、そうでなければ死ぬ間際まで比較的元気です。ほんとうの最後になると息が苦しくなったり、肺がんそのものの痛みが出てきて、酸素や鎮痛剤の投与が始まります。
酸素を吸ったり、普通の麻薬を使ったりしても苦痛が取れなくなったら、かの有名なモルヒネの出番です。モルヒネは息が苦しい感覚や痛みを取り除いてくれますが、正常な呼吸をも抑制してしまう作用があります。モルヒネを導入するということは、それに伴う死のリスクがあるということです。実際のところ、モルヒネを始めてからほどなくして、患者さんは眠るようにして死んでいきます。「最期は苦しまず、楽に逝けてよかったのではないでしょうか」という話になります。
今日ではインターネットであらゆる情報が手に入りますが、こういう生々しい話はあまり出てきません。
たとえばグーグルで「心筋梗塞」と検索すると、病気に関する豊富な情報が出てきます。心臓を栄養する血管が詰まる病気であること、治療としてカテーテルでその詰まりを解除すること、高血圧や糖尿病がそのリスクになること……。その一方で、心筋梗塞になった人が実際にどういう死に方をするのか、どんな気持ちになり、どんなことを考えながら死んでいくのか、そしてその家族がどういう思いで過ごすのか……そういう話についてはあまり詳しく書いてありません。
死について考えるというのは、こうした生々しい情報に触れながら、自分や自分の家族がどのようにして死んでいくかを考えることだろうと思います。
末期肺癌患者の決断
しかし、ここまでの話はまだ客観的な情報に過ぎません。
死について考えることは、たぶん健康な我々が想像しているよりもう少し壮絶なプロセスです。自分が健康なうちは、そこにある苦痛を体験することができないからです。
死について考えるとはどういうことか、教えてくれた患者さんがいます。僕にとって忘れられない患者さんの1人です。
その患者さんも肺がんでした。70歳くらいの男性で、数日前から息が苦しくて動けなくなり、救急車で運ばれてきたのでした。
指導医とERに行ってカルテを開いてみると、当時ほとんど素人に近かった僕にも、進行した肺がんが全身に転移していることがわかりました。手術はおろか化学療法も難しい、いわゆる末期の状態で、余命1カ月といったところでした。
この時点で彼に残された選択肢はいくつかありました。
まず、放射線を使った治療で急変のリスクを少しでも下げるという方法。彼の場合は上大静脈という太い静脈を転移巣の1つが圧迫していて、これが少しでも大きくなると静脈閉塞による急変のリスクがありました。この転移巣に放射線を当てることで、そのリスクを減らせる可能性があるということでした。当然ながら、この方法には放射線による副作用があります。
次に、そうした治療はせずに、ホスピスに入って安らかに余生を過ごすという方法。ホスピスというのは苦痛緩和に特化した施設で、積極的な治療を行わないと決めた末期の患者だけが入ることができます。
しかし、彼がホスピスに入るためには、末期がんであるという診断を確定することが必要でした。CTの画像から考えれば十中八九は肺がんなのですが、本当のところは顕微鏡で組織を見てみなければわかりません。組織の採取には気管支カメラを飲んだり、皮膚から肺に針を刺したりと苦痛が伴います。検査の結果が出るまでに時間もかかりますし、そもそも、行先のホスピスが決まるまでにもそれなりの時間がかかります。
そこで最後の選択肢は、こうしたいっさいの面倒事を排除し、普通の病院で可能な限りの苦痛緩和をしながら最期を迎えるという方法です。ホスピスのように苦痛緩和に特化した場所ではありませんが、前述のとおり、普通の病院でも鎮痛剤や麻薬の処方、酸素投与など、痛みや息苦しさを取り除く処置はできます。
こうしたいくつかの選択肢を本人に提示したうえで、実際に死を迎えるまで何をするか、本人の考え方に合うものを選んでもらうわけです。
ただし、これはがんの告知をする場合の話。そもそも本人や家族の状況次第では、がんの告知自体をしない場合もあります。
また、普通の患者さんであれば、まず自分が末期がんであることを受け入れること自体に少なからぬ時間がかかります。ようやく受容ができてから、どういう風に最期を迎えたいか、家族と相談しながらゆっくり決めていくというのが一般的です。
今回の患者さんはどういう反応をするだろうかと思いながらベッドサイドに行くと、患者さんが苦しそうに呼吸をしながらも、どこか悟ったような顔をして待っていました。
我々を目にするなり、彼は開口一番こう言いました。「もういいんだよ。生きてたってしょうがない。いろいろやらなくていいから、できるだけ苦しくないようにしてくんないかな」
彼の治療方針は、その場で「緩和」に決まりました。すぐに入院し、その日から鎮痛剤の投与や咳止めの吸入など、症状を取り除くための治療が始まりました。
死にゆく患者が語ったこと
入院して数日は苦しそうにしていたものの、治療が軌道に乗ってくると落ち着いて話もできるようになりました。時間のあるときに病床に行くと、彼自身の考えについて少しずつ話してくれました。
結婚もしないまま60歳を過ぎ、兄弟とも疎遠で、最近は誰ともかかわりがなくなってしまったこと。仕事もないので生活保護を受けながら、日々やることもなく過ごしていること。
本当は1年くらい前から肺癌の可能性を指摘されていたけれど、その時は別に死んでもいいと思って放っておいたこと。苦しくて身動きもとれなくなってから救急車を呼んだものの、その時には手遅れになっていることが自分でもわかっていたということ。自分で放っておいたものの、いざ末期癌で死が近いことを聞かされて、それを受け入れるのにはそれなりの苦痛があったこと。
「もう遅かったんだよな」と彼は言いました。「だから、余計なことはしないでいいです。これだけやってくれて、もう満足です」
彼にそう言われて、我々は本人が望まない処置のいっさいから手を引きました。経過中に肺炎になり、抗生剤の点滴が必要になった時も、点滴なんてしたくないんだと言われたのでやめてしまいました。酸素マスクすら邪魔だと言って外してしまうことがありましたが、我々もあえて装着を強要しませんでした。
入院から2週間くらいして、慢性期病院へ転院することが決まりました。
転院先へ搬送する救急車の中で、他愛もない話をしながら繰り返し「ありがとう」と言われました。「死ぬ前に太田さんとビールでも飲みてえなあ、だめか」などと言いながら、穏やかに笑っていました。死を悟り、受け入れた人はこういう顔をするのかと思いました。 最後に別れるとき、どちらからともなく交わした握手を僕は一生忘れないだろうと思います。
おわりに―死について考える―
最初に肺がんかもしれないと言われた時、彼は「別に死んでもいい」と考え、検査や治療をする選択肢を放棄しました。
しかしその1年後、呼吸が苦しくなってはじめて、彼は本当の意味で自分の死を予感するわけです。はじめはそれなりの精神的苦痛があったのでしょう。しかし、自分がもう手遅れであることを悟り、その上でむやみな延命に意味を感じられなかったことから、彼は最終的に「やはり死んでもいい」という結論を出しました。
同じ「死んでもいい」でも、天と地ほど違います。
彼が経たこのプロセスこそが、まさに死について考えるということだと思います。
さて、我々は彼がした選択について、なにかを意見できる立場にあるでしょうか。
もちろん答えはノーです。我々は末期癌の苦しさも、肺癌で死が目前に迫っている心境も、彼と共有することができません。できない以上は医師であれ、彼の親族であれ、どうこう言う権利はありません。肺癌の可能性を放置していたことも、最後に延命治療を拒否したことも、すべて彼自身の選択として尊重されるべきです。
同じ局面にあって、化学療法のフルコースを希望する方もいます。それも1つの選択です。いずれにせよ、実際に死を目前にして、本人なりの価値観で、自分の死ぬまでの時間を選ぶことが、死について考えることだと思うのです。そしてその思考は、健康な我々には決してトレースすることができません。
それでは、翻って冒頭の安楽死の女性のことを考えたとき、健康な我々は彼女の死についてなにかを語る権利があるでしょうか。
これは意外と難しい問題だと思うのです。安楽死の善悪を考えるのが難しいのではありません。健康な人々が安楽死の善悪を問うということそれ自体が、構造的に大きな問題を孕んでいるように思われます。

