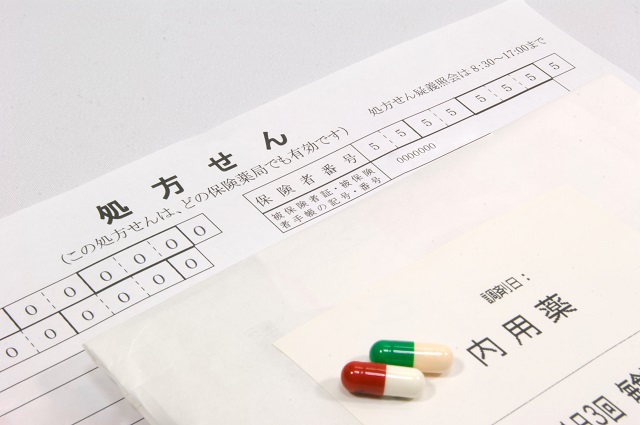病院に行って診察してもらうと、お薬をもらうための「処方せん」が発行されます。近くの薬局にもっていって、お薬をだしてもらう引換券みたいなものですが、この処方箋をじっくりと見たことのある方はいらっしゃるでしょうか?
薬剤師は処方せんに書かれている情報をもとに調剤を行い、患者さんに渡します。この処方せんに書かれている情報ってどんなものなのか、興味ありませんか?
処方せんの読み方を知っていると、間違って処方・調剤されていないか、保険は正しく使われているか、ジェネリックに変更できるお薬はどれかなどがわかります。そこで今回はこの処方せんの読み方についてお伝えしていきたいと思います。
それでは早速処方せん例をもとに詳しく見ていきましょう。

出典:厚生労働省|処方箋様式をもとにいしゃまち編集部作成
1.保険情報
病院で提示した保険証の情報が記入されています。
また保険証のほかに乳幼児医療などの受給者証があれば左側あるいは右下の欄に記載されます。
薬局でも保険証の提示を求められるのは、この欄が病院側で間違って記入されていないか確かめるためです。
2.患者情報
患者氏名・生年月日・性別、また保険の被保険者・扶養者の区分が記載されています。
まれにですが、病院側が間違って違う患者さんの処方箋せんを渡してしまうこともあるので、自分の名前が書かれているか確認しましょう。
3.病院処方医情報
病院所在地・電話番号・病院名、そして診察した医師の名前・押印などが記載されています。
処方医の名前は自著で記入していれば押印は必要ありませんが、印字された名前の場合必ず押印が必要となりますので、氏名の横に押印がない場合は病院に問い合わせてください。
4.交付年月日
処方せんが発行された日にちが記載されます。
特に指示がない場合処方せんの期限は4日間となっており、この期間を過ぎると薬局では取り扱ってもらえない場合が多く、もう一度病院に行って再発行してもらう必要があります。
今回の例によると11月15日発行ですので、11月18日までには薬局で受け付けてもらわないといけません。知らない方も多いので、必ず4日以内にもっていくようにしてください。
5.処方内容
実際に出される薬の情報が記載されています。
薬には一般名と商品名が存在しており、処方せんにはどちらを記入してもよいことになっています。商品名とは製薬会社がつけた名前のことで、一般名とはその薬の成分そのままの名前のことを言います。例えば痛み止めで有名なロキソニンという名前は商品名で、一般名はロキソプロフェンといいます。
一般名で書かれている場合はわかりやすく【般】と薬名の前につけられていることが多いです。一般名の場合は、先発品・ジェネリック(後発)品どちらを選んでも大丈夫ですが、なるべくジェネリックを使う必要があるため、先発で出してもらいたい場合は理由が必要になります。
また、商品名で記載されていても、左横の「変更不可」にチェック✔がはいっていない場合はジェネリックが存在すればジェネリックに変更することが可能です。
薬局に行った際、おそらくジェネリックに変えられるものは変えてもよいかなどを聞かれると思いますが、処方箋をみておくことで、どれをジェネリックに変えるかを事前に知ることができます。
「先発品」「ジェネリック医薬品」って?
新しく開発された医薬品のことを「先発品(新薬)」といいます。新しい薬を開発すると、製薬会社はその薬に対して特許を取得し、独占的に販売することでその開発費用を回収します。しかし特許が切れると、他の製薬会社が先発品と同じ有効成分や製法で薬を作ることができるようになります。ここで作られるのが「ジェネリック医薬品(後発品)」で、先発品と比べると開発にかかる年数もコストも少ないため、安価での販売が可能なのです。
ジェネリック医薬品の品質や効能は、先発品と変わりません。

それでは今回の例について、もう少し詳しく見ていきましょう。
1)○○錠250mg2錠
1日1回朝食後 3日分
今回は商品名で記載されていますが、チェックが入っていないためジェネリックに変更可能です。
○○は商品名、錠は剤型(他にカプセルやシロップなど)、250㎎は規格でお薬によっては250㎎、500㎎などが存在するため指定しています。
また2錠は1日に服用するお薬の量のことです。今回は1日1回朝食後といった用法が指示されているため、朝に2錠飲んでくださいということです。
上記の例では出された日数が3日分ですので、実際に渡されるお薬は2錠×3日分の6錠になるはずです。
この他、今回の例にはありませんが「ロキソニン 1錠/回 毎食後 7日分」のように、1回に服用する量を記載する医師もいます。
渡されたお薬がこの内容とあっているか、しっかりと確認しましょう。
2)般○○○○錠60㎎1錠
痛い時 5回分
こちらは一般名で処方されているので、ジェネリックにしてもらうことが可能です。
今回は頓服で出されています。これは、決まったタイミングに飲むのではなく、「症状が出たときに適宜飲むように」という指示です。上記例では、痛いときに1錠飲むよう指定しています。
2)△△液7%30㎖
1日数回
こちらは商品名で処方されており、さらに左横にジェネリック変更不可のチェックが入っているため、先発品である△△液7%でしか出すことはできません。
上記の例では「△△液7%」は外用のうがい液であるため、30㎖というのは全量のこと(1本30㎖)です。処方せんには薬の薄め方などの指示は書かれていないため、詳しい使い方は薬剤師や医師の指示に従ってください。
このように処方箋を事前に確認しておき、実際渡されたお薬の内容や量が間違っていないか確認しましょう。特に250㎎や500㎎などの規格が正しいかなどは要チェックです。
6.ジェネリック変更不可の署名
⑤でも軽く触れましたが、薬品名の左横にチェックがはいっているとジェネリックに変更することができません。しかしもしこの署名欄が空白で署名されていない場合はジェネリック変更不可のチェックは無効となります。
ただこちらは記入漏れ・押印漏れしやすい箇所であるため、注意が必要です。
7.残薬確認
平成28年度より新たに追加された項目です。
薬局側で患者さんの残薬状況を確認した際に、病院に対してどのような対応をとればよいかについて書いてあります。
□保険医療機関へ疑義照会した上で調剤
□保険医療機関へ情報提供
もし「保険医療機関へ疑義照会した上で調剤」にチェックが入っていれば、今回から処方日数を調整して残薬を使い切らせることになることが多く、「保険医療機関へ情報提供」にチェックが入っていれば、次回処方時に日数調整することが多いです。
8.薬局記入欄
調剤した日にち、薬剤師名などを調剤後に薬局側が記入するため、処方せんが発行された時点ではなにも書いていない状態です。
まとめ
処方せんを見ることもなくそのまま薬局に渡してしまう方も多いと思いますが、実は処方せんには以上のようなたくさんの情報がつまっており、事前にどのようなお薬がでるか、ジェネリックになるかなどが確認できるのです。
特に病院の押印漏れなどはそのまま持っていくと薬局側で病院に電話する必要などがでてくるため、お薬が出てくるまでの時間が長くなってしまいます。
また処方箋に書かれているお薬の規格とだされたお薬が一緒かなどは非常に重要ですので、ご自身でも確認できるよう、処方せんの読み方も覚えておくとよいでしょう。