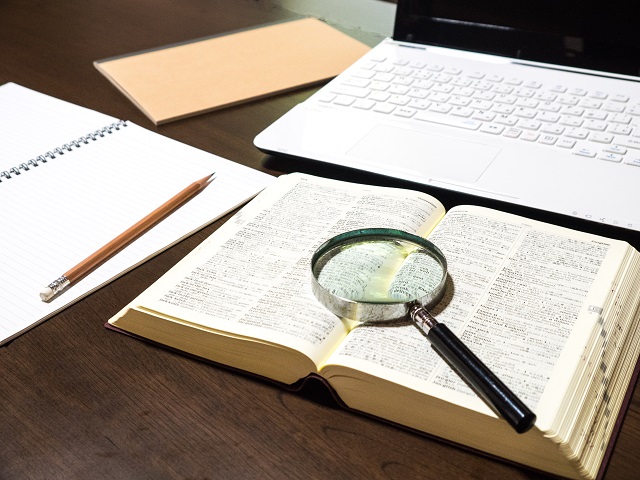- アレルギー
-
読み方アレルギー英語allergy
身体を守るための免疫の仕組みが過剰反応を起こし、食べ物や花粉など、本来であれば身体に害を与えない物質に対しても攻撃をした結果、様々な症状が出てしまうことをいいます。
- 依存症
-
読み方イゾンショウ英語dependency
ある薬物などを摂取したときに生じる特定の精神的・身体的状態をいいます。日常生活に支障をきたしているにも関わらず、お酒や薬物、ネット、ギャンブルなどにのめり込み、自分の力だけではやめることができなくなった状態です。
- 医薬部外品
-
読み方イヤクブガイヒン英語quasi drug
薬品、医薬法によって「医薬品」と「医薬部外品」とに区別されています。このうち、医薬部外品は人体に対する作用が穏やかなものをいいます。薬用化粧品や薬用はみがき、殺虫剤などがこれにあたります。
- 医療用医薬品
-
読み方イリョウヨウイヤクヒン英語ethical pharmaceutical
医薬品のうち、医師の処方を受けて、病院の薬局や院外の調剤薬局が患者に提供する薬を指します。効果は高いものの、その分副作用のリスクもあるため、医師の処方箋なしでは販売できません。
- 因子
-
読み方インシ英語factor
ある結果を起こすもとになる要素・要因のことです。
- 陰性
-
読み方インセイ英語negative
検査において反応がないことです。例えばインフルエンザの検査で「陰性」だった場合、検査を受けた人はインフルエンザウイルスが検出されないことになります。
- 院内感染
-
読み方インナイカンセン英語nosocomial infection
病院の中で起こるあらゆる感染を総称して院内感染といいます。患者や面会人など人を介するものと、診療用の医療器材や空気中の病原体を介するものがあります。院内感染は抵抗力の弱い患者に起こりやすく、集中治療室(ICU)や新生児室での感染が問題になっています。
- インフォームド・コンセント
-
読み方インフォームド・コンセント英語informed consent
ある治療法などについて、患者が医師から十分な説明を受け、正しく理解して納得したうえで同意することです。医師と患者とがともに治療について考え、治療方法を選択することを指します。「IC」と略すこともあります。
- ウイルス
-
読み方ウイルス英語virus
病原体の一つで、細菌よりずっと小さく、電子顕微鏡でようやく見えるくらいの大きさです。細菌は生物に寄生せずに自分で増えることができますが、ウイルスはほかの生物の中でしか増えることができません。また、細菌には抗菌薬が効きますが、ウイルスには効果がありません。
- うっ血
-
読み方ウッケツ英語stasis
「鬱血」と書きます。何らかの原因で静脈の血流が妨げられたり、心臓の働きが弱まったりした時に、身体の一部に静脈の血が異常に多くたまった状態です。
- うっ滞
-
読み方ウッタイ英語retention
血液やリンパ液などが正常に流れず、一定の場所にたまってしまった状態を示します。
- 運動療法
-
読み方ウンドウリョウホウ英語exercise therapy
身体を動かすことで症状の改善を目指す治療法のことです。
- 壊死
-
読み方エシ英語necrosis
組織の一部が死ぬことを意味します。壊死した部位を放置しておくと、その部分が腐敗し、さらなる障害が生じる場合があります。
- 壊疽
-
読み方エソ英語gangrene
壊死した組織が腐敗し、褐色または黒に変色した状態を壊疽といいます。動脈硬化による血流障害や、神経障害などが原因となります。
- エビデンス
-
読み方エビデンス英語evidence
「この薬や治療法・検査方法が適している」といえる根拠のことです。医療に関した研究分野では、実際に多くの患者さんに協力してもらうことでこうした根拠が蓄積されており、医療の進歩に多大なる貢献が成されています。
- 嚥下
-
読み方エンゲ英語swallowing
飲み込むことを表します。
- 炎症
-
読み方エンショウ英語inflammation
身体が有害な刺激を受けたとき、これを取り除こうと防御反応が起こります。一般的に、その反応が起きている場所は「熱」「腫れ」「赤み」「痛み」などを感じます。これが「炎症」です。
例えば、肺に入ってきた細菌やウイルスに抵抗するために肺が炎症を起こしている状態が肺炎です。アレルギーの場合も、外から入ってくる物質に反応して、身体が炎症を起こします。 - 黄疸
-
読み方オウダン英語jaundice
肝臓や血液の異常によって、皮膚や白目の部分が黄色くなることです。肝炎や肝硬変、肝硬変のほか、通常は血管に入らない胆汁(たんじゅう)の成分が、肝臓につながった血管に入り込むことで起こります。血液の場合、赤血球が一度にたくさん壊れることによって起こります。どちらも、血液中のビリルビンという物質が増加して、皮膚や粘膜にたまることで、黄色くなるのです。