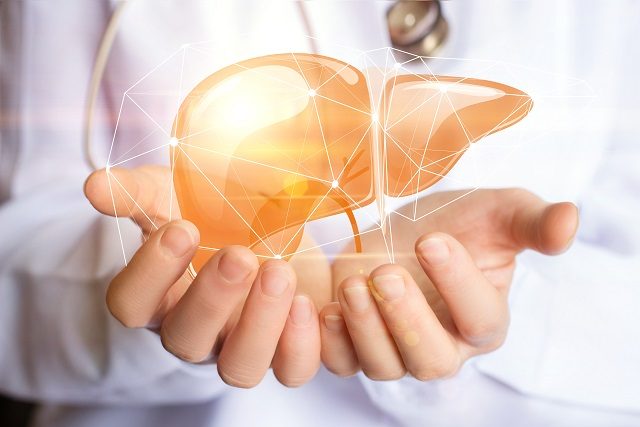肝臓は文字通り「肝心かなめ」の臓器。肝臓の機能が著しく低下している状態は肝不全と呼ばれます。肝不全はどのような原因で起こり、どのような症状がでるのでしょう?
化学工場としての肝臓の働きとは?
なぜ肝臓は「肝心かなめ」の臓器と呼ばれているのでしょう。それは肝臓が生体内の化学工場としての重要な働きを担っているから。肝臓の働きは多種多様ですが、代表的な働きとしては以下のようなものがあります。
1.エネルギーの保存、供給
腸で吸収された糖や脂肪、タンパク質は、化学工場である肝臓に運ばれて蓄えられます。そして、身体の中で栄養分が不足すると、必要な栄養分を肝臓で合成し供給してくれるのです。
2.有害物質の解毒
肝臓はアルコールや薬、老廃物などの有害な物質を分解し、身体に害が及ばないよう無毒化してくれます。
3.胆汁の生成・分泌
不要になった物質を再利用して胆汁を生成します。胆汁は脂肪を吸収するのに重要な働きをしています。たとえば、ビタミンは脂溶性と水溶性があり、脂溶性ビタミンは胆汁がないと吸収できません。エネルギーとして重要な脂肪を体内に取り込むのにも胆汁が必要です。
肝不全の原因
ではどのような場合に肝臓の働きが低下するのでしょう?肝不全の原因として、肝炎ウイルスやアルコール、薬の副作用などがあります。
- 肝炎ウイルス
- アルコール
- 薬剤
- 自己免疫性肝炎
- 原発性胆汁性肝硬変
- 原発性硬化性胆管炎
- 脂肪肝など
肝不全は、数日から数週間で急性に進行する場合(急性肝炎)と数か月から数年かかって徐々に進行する場合(慢性肝炎)があります。
肝不全で起こる症状

肝不全で起こる症状は以下のようなものがあります。
1.低栄養
肝不全になると栄養分を保存する能力がなくなるため、低栄養状態に陥ります。例えば肝硬変の状態になると、健常者の3日間の絶食に近い状態にわずか半日の絶食で陥るとされています。
2.腹水
肝不全になると肝臓でタンパク質を合成することが難しくなります。血液中に水分を留めておくためにはタンパク質(アルブミン)が必要なのですが、低タンパク状態が続くと血管内に水分を留めておくことができず、血管の圧が亢進することも伴い、お腹に水が溜まってきます。
3.出血傾向
血液を固める凝固に必要なタンパク質が不足するため、アザができやすく血が止まりにくくなります。
4.肝性脳症
小腸で吸収できなかったアミノ酸は腸内細菌のエサとなります。そして腸内細菌がアミノ酸を食べたあとにアンモニアが排出されます。また生体の代謝物としてもアンモニアは生成されます。
通常アンモニアは肝臓で害の少ない尿素へ分解されますが、肝不全になるとアンモニアを分解することができません。アンモニアが多くなると脳が障害を受け意識障害をきたします。これを肝性脳症といいます。
5.黄疸
肝不全になると胆汁の成分の生成や分泌が障害されるため、赤血球が壊れる際にできるビリルビンという色素により全身の皮膚や目が黄色くなる黄疸という現象が起きます。
その他にも、吐き気や食欲不振、全身倦怠感などの症状が出てきます。また免疫力も低下するので感染症にもかかりやすくなります。肝不全が進行すると肝腎症候群をきたし腎臓の機能も低下します。
肝不全の治療
肝臓は正常な状態なら3/4切除しても元に戻る能力があるとされています。また肝臓は沈黙の臓器と呼ばれ、肝臓の機能が少しぐらい低下しても症状はほとんどありません。逆に肝臓から症状が出てきた場合というのは、肝不全がかなり進行している状態と考えて良いでしょう。
進行した肝不全では集中治療室での全身管理が必要になることがあります。肝臓の再生能力が戻るまで人工肝補助療法(血液浄化療法)を用いることもありますし、多くはありませんが肝移植の適応となることもあります。
いずれにしても肝不全まで至った場合は治療が困難なことが少なくありません。肝臓の機能は非常に複雑なので、肝不全に陥った肝臓を全面的に置き換えられる人工的な支援装置がないのです。
まとめ
いかがですか?急性肝炎からの肝不全は予測が難しいのですが、慢性肝炎からの肝不全は予防することが可能です。C型肝炎は新薬により根治可能の疾患となっていますし、B型肝炎も根治とまではいかなくても進行を抑えることは可能です。他の肝臓の病気でも多くは進行を予防できます。
注意すべきは近年増えている肥満やアルコールによる肝炎です。こちらは病気と自覚している人が少なく、気が付いたら肝硬変、さらには肝不全となっていることも少なくありません。肥満やアルコールによる肝炎はジワジワと進行していくことが多いため、肝炎を指摘された場合は医療機関に相談した方が良いでしょう。