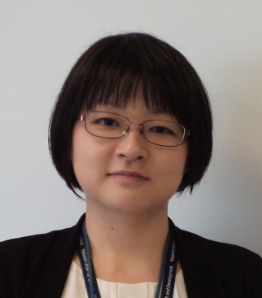病気は、患者さんやご家族のこころに少なからぬ影響を与えます。病気そのものに対する不安はもちろん、治療を受けることへのストレス、家族として何ができるのかといった葛藤など、その影響は多岐にわたります。
国立成育医療研究センターでは、児童・思春期リエゾン診療科が心理社会的支援を担っています。リエゾンとは「身体の症状に悩む患者さんの精神面をサポートすること」を表していますが、小児に特化したリエゾン科があるのは、日本では成育医療研究センターだけです。このリエゾン診療科は、子どもたちの慢性疾患を治療する上で重要な役割を果たしています。
今回は、国立成育医療研究センター 児童・思春期リエゾン診療科から2名にお話を伺いました。まずは、心理士・松元和子さんの取材をお届けします。昨年連載した「小児がんを考える:国立成育医療研究センター 小児がんセンター こどもサポートチーム」とあわせて読んでいただければと思います。
「黒衣」として隙間を埋め、意見を取り持つ
―松元さんは「児童・思春期リエゾン診療科」の担当とのことですが、この診療科目はそもそも、どんなことをする科なのでしょうか?
簡単に言うと、身体の病気を持つ方の心理社会的な面をトータルに診て、その方が治療を続けながらより良い生活を送っていくためのお手伝いを、主治医と協力しながら行うことをお仕事としています。
いわゆる精神科(精神科医が中心となって治療に取り組む)とは違い、メインとなるのは身体の治療を行う主治医や看護師です。患者さんの中には精神的な問題を抱える方もいて、その方たちには治療としてカウンセリングも行いますが、基本的なスタンスとしては身体の治療を支えるサブの役割ですね。
―精神科とは違い、身体の病気や症状に付随して起こるこころの症状を支えているのですね。
そうですね。もちろん、薬の副作用で精神科的な症状が出てくることもあるので、そういう場合はリエゾン科の医師が薬の調整をすることはありますし、カウンセリングをしっかり行った方が良いようであれば心理士が担当することもあります。
ですが、リエゾン活動における心理士は基本的に、隙間を埋める職種です。メインではなく、(舞台上で主役を支える)黒衣のようなものだと思っています。患者さんやご家族と主治医・看護師との意見がすれ違ってしまったとき、「もしかしたら、こんな風に感じているのかもしれませんよ」と通訳する役割ですね。
特にお子さんの場合、自分の考えを言葉で表現するのは難しいことです。遊びなどを観察しながら言葉にならない想いを代弁し、先生たちが治療に役立てられるようにお伝えします。
反対に、主治医や看護師の言葉に敏感に反応するお子さんやご家族に対しては「そう受け取ってしまいますよね、でもこういう意味かもしれませんよ」と、不安な気持ちに寄り添いつつ、通訳をすることもあります。
スタッフ間の橋渡しを行うことも
―お子さんと医療者との橋渡しをするのがお仕事の中心ということですね。
そうですね。あとは、医療スタッフの支援も大切だと感じています。それが、間接的に患者さんを支援することにつながります。
スタッフは、職種によって大事にしているものが異なります。主治医だったら病気を治すことが第一ですが、看護師はそれ以外にも退院後のケアを自分でできるように教えるなど、生活全般を気にかけています。また保育士など、お子さんが社会に戻ったときのことを考え、病院の中での成長発達を中心に気を配っているスタッフもいます。
それぞれの職種が皆、各々の信念を持って一生懸命治療にあたっています。それゆえに、どうしてもぶつかることがあるんです。より良い治療を目指す上で意見を闘わせることはとても大切ですし、避けては通れません。でも、ときにそれが行き過ぎて、がんじがらめになってそこから動けなくなってしまうことがあります。そんなときこそ、医療の素人である心理士をうまく使ってほしいなと思います。
私たちは治療に直接関与しません。なので、一人の人間として当然感じるであろう、でも医療者であるがゆえに出せないような葛藤を、ぽろっとこぼしてもらえるような存在になれたらと思っています。話を聴いて、相槌をうつぐらいしかできないかもしれませんが、日々緊張を強いられるスタッフがほっと一息つけるような時間を提供することも、心理士の役割のひとつです。
―こどもサポートチームでは、子どもたちのこころを支える職種はほかにもいると思います。そうした職種との役割分担はどのように行っていますか?
こころのケアは、実は患者さんやご家族にかかわる人全員で行っていることです。そして、重なり合ってもいいと思っています。その中で互いの職種を信頼し、「今回は任せた」「今回は任せて」と気軽に言い合えるのが理想的なチームだと思います。
お子さんとの“相性”と言ってしまうとそれまでですが…患者さんにとって自分の気持ち、それも蓋をしておきたいようなドロドロした気持ちと向き合うのは本当にしんどい作業です。「ただでさえ身体の病気を持っているのに、どうしてそんなことをしないといけないの?」と思う人もいて当然ですよね。そんなときに心理士が来て「さあ、話を聴かせてください」と言っても、人によっては受け入れられないと思うんです。
だから、「この人となら向き合える」と思える人を患者さん自身が選んでいいと思っています。それは保育士やCLS(チャイルド・ライフ・スペシャリスト)、主治医や看護師かもしれません。彼らがこころのケアを行い、私たちは後方支援をする、という形もありだと思います。
次のページ:「手を離す」まで、一緒に答えを探す