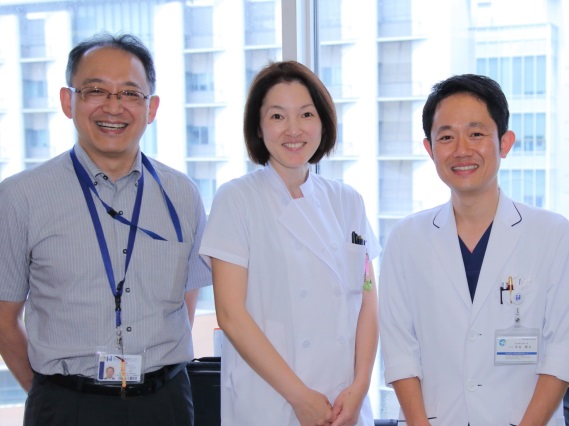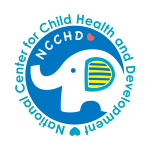この連載の中で繰り返し伝えているように、小児がんは「治る病気」です。一方、子どもたちの生活やその後の人生に大きな影響を与える病気でもあります。
病気にかかった子どもたちは、病棟でとても濃厚な時間を過ごします。そのひとときを共に過ごす医療従事者の取り組みは、小児がんという病気を知る上で欠かすことのできない話題です。
国立成育医療研究センター 取材連載、最終回は医師・塩田 曜子先生のインタビューをお届けします。ぜひ、これまでに紹介した9名の取り組みと合わせて、主治医として子どもたちと関わる塩田先生の取り組みを知っていただければと思います。
※写真:病室の窓からの風景
正確な診断を素早く行うために
―小児がんの子どもたちと関わるにあたり、治療やコミュニケーションの方針など、様々な決定の中心になるのが「主治医」だと思います。診断を含め、“決める”という場で大切にしていることはありますか?
まずはどこに何がどれだけあるのか、病気の本体が何か、絶対に間違えないように徹底的に調べます。
それは私一人ではできません。放射線の診断部の医師や、病理医、検査を行う技師、実際にがんを取ってくる外科医…外科医と言っても、小児外科だけでなく、脳神経外科や整形外科、形成外科や耳鼻科や眼科など、がんの発生部位によって様々ですが、彼ら全員が一斉に、スピード感を持って調べます。お子さんのためにも早く相手(病気)を決めて、日本中・世界中の治療を徹底的に調べ、今一番良いであろう治療法を提示した上で親御さんと一緒に考えて進めるという流れです。
成育はスタッフが揃っているので、診断の速さはとても子どものためになっていると思います。
―とにかく早く、正確な診断を行うために、たくさんの医療従事者が関わっていくのですね。
そうですね。その中において主治医が中心にはなりますが、主治医はかえって視野が狭い部分もあります。多くの人の目が入った方が、その子のことを冷静に判断できます。それに、主治医が「この痛み止めが良いだろう」と思っても、緩和ケア医から「こちらの薬はどうですか?」と提案があれば、「そういう考えもあったか」と視野が広がるのです。
こどもサポートチームができ、多職種が関わるようになったことで、主治医が自分一人で抱えなくて良くなりました。以前はどちらかというと、その子のことは自分自身が全て抱え込んで、自分だけで守っているという意識が強かったと思います。でも今は、周りのプロに委ねられるところはどんどん委ねています。その方が、子どもと家族には大きなメリットとなります。
こどもサポートチームができて3年になり、とてもうまく機能するようになってきました。特にこの1年は、緩和ケア科の余谷先生が加わって、治る子に対するケアでもできることが増えましたね。
―チームでの医療にあたっては、カンファレンス(会議)などでのコミュニケーションが非常に重要だと想像します。
はい。ただ、(こどもサポートチーム全体の)カンファレンスだと発言しにくいスタッフもいるとは思っています。ですから、他のカンファレンスも度々設けています。
例えば、保育士や心理士、ソーシャルワーカーなどが参加するPSCカンファレンス。そこでは、多職種がざっくばらんに話をしています。ただ、彼らは治療方針については分からない部分もあります。「この子、次の抗がん剤はいつ?」「外泊はいつ行けそう?」などですね。「もう少し早く外泊に行ければ、お母さんの気持ちもおさまる」などという時、私がその場で他の医師に電話をして聞いて、すぐにみんなに伝えれば議論が進むことがあります。その橋渡しが大事だと思っています。
小児がんの子たちは、治療方針も含め、状況がころころ変わります。なので、スピード感がないと多職種も動きづらいのです。
次のページ:まずは、子どもたちと「仲良くなりたい」