脳梗塞の発生メカニズムや症状は「脳梗塞が起こる原因と症状4つ!前兆はあるの?」で述べていますが、死亡者は、国内で年間6万2223人におよぶ病気です(厚生労働省 平成28年人口動態より)。日本人の死亡原因として第4位である脳血管疾患のうち、半分以上を占めています。
その脳梗塞になってしまったら、どのような治療が行われるのでしょうか。
また、後遺症が残った場合に行われるリハビリとその予後についてご紹介します。
脳梗塞の診断
脳梗塞が発症すると、詰まった血管の支配領域の脳がダメージを受けます。
症状はダメージを受けた脳の部位によって違いますが、症状などの診察所見と以下のような画像所見で診断されます。
1.CT検査で脳内出血の有無を確認
脳にX線を当て、コンピューターで断面画像にします。
CT検査で脳内出血があるかどうか、脳梗塞があるかどうかがわかります。
脳梗塞を疑う症状がある場合、まずはCT検査で脳内出血があるかどうかを確認します。
その結果、黒い影が見られれば脳梗塞と診断されます。
※CT検査=computed tomography検査
2.MRI検査で詳細確認
磁気を脳に当てて、コンピューターで画像化します。
CTでは分からないような小さな脳梗塞も、MRIなら確認することができるのです。
脳梗塞が起こったばかりの時はDWI(diffusion weighted imaging)と呼ばれる拡散強調画像法で検査します。
つまり、脳梗塞を疑い、救急搬送された際に、MRI検査が可能であれば、CT検査ではなく、まずMRI検査が行われます。
その他、血管だけを強調して写し出すMRA(magnetic resonance angiography)という撮影方法を行うと、血管に狭窄や閉塞があるかどうかを確認することができます。
※MRI=magnetic resonance imaging
3.頸動脈エコー、脳血管造影検査
更に詳細に調べる時に行われます。頸動脈エコーは頸動脈を超音波で検査するもので、動脈硬化の状態や狭窄、閉塞があるかどうか調べることができます。
脳血管造影検査は造影剤を脳動脈に流して血管を撮影するものです。
血管の狭窄、閉塞した場所をより正しく診断することができます。
脳全体の血管をかなり詳しく知ることができますが、0.1~1%の確率で造影剤アレルギー(ショック)などを起こす危険もあります。
脳梗塞の治療

脳梗塞が起こった時にどのような治療を行うのかについてご紹介します。
急性期治療は時間との勝負です。発症後、何時間経過したかどうかで治療が変わります。
※脳卒中治療ガイドライン/グレードA(エビデンスが高い)を中心に解説
脳梗塞急性期の治療
1.血栓溶解療法(rt-PA)
発症から4.5時間以内の超急性期脳梗塞に対し、アルテプラーゼ(商品名:アクチバシン、グルトパ)という血栓を溶かす作用のある薬剤を点滴で投与します。
血栓を溶かす作用があるため、少しでも脳内出血がある場合は使われません。
また、その他に出血リスクが高いと判断される場合には使用できません。
※血栓溶解療法=rt-PA(recombinant tissue-type plasminogen activator)
2.血管内治療(脳血栓回収療法)
血栓を溶かす血栓溶解療法(rt-PA)に対し、血栓回収療法は血栓を摘出することで血管の再開通を目指す治療法です。発症後8時間以内の超急性期脳梗塞にも適応が有り、rt-PAの適用がない場合・rt-PAで効果が見られない場合に選択されます。
近年新しく取り入れられるようになった治療法で、2010年のメルシー(merci retriever)、2011年のペナンブラ(Penumbra system)をはじめ、新しいデバイス(治療を行うための器具)が次々に認可されています。
なお、本治療は対応できる病院が限られていることが課題です。
3.抗凝固療法(アルガトロバン)
発症から48時間以内で、脳梗塞の大きさが1.5cmを超える非心原性脳梗塞に対しアルガトロバンと呼ばれる薬剤を点滴で投与します。
アルガトロバンは血栓の原因となる血液の凝固を阻害する作用があります。これ以上、脳梗塞がひどくならないようにするものです。
4.抗血小板療法(アスピリン、オザグレルナトリウム)
抗血小板薬は、血液中の血小板の凝集を阻害する作用があり、血液をサラサラにすることで新たな血栓をできにくくします。
いずれも心原性脳塞栓症を除く脳梗塞に対して投与されており、アスピリンは発症から48時間以内に経口投与、オザグレルナトリウムは発症から5日以内に点滴投与されます。
5.脳保護薬(エダラボン)
エダラボンと呼ばれる脳保護薬を併用して使うことがあります。
しかしエダラボンの効果についての臨床的な根拠は少なく、欧州ではまだ試験段階なのが現状です。
エダラボンには、フリーラジカル(脳にダメージを与える物質)を消去する作用があり、発症24時間以内の脳梗塞の治療法として認可されています。
脳梗塞慢性期の再発予防
脳梗塞の急性期治療では「できるだけ脳梗塞の被害を広げない」ために、血栓を溶かし一刻も早く詰まった部分を再開通させます。
急性期治療で脳梗塞の拡大を抑えた後は、脳梗塞が再発しないための治療に移ります。
1.抗血小板療法
非心原性脳梗塞の再発予防には抗血小板薬を内服します。
現在ではアスピリン、クロピドグレル、シロスタゾールといった薬が推奨されています。
2.抗凝固療法
心原性脳塞栓症に対する投与は抗凝固薬のダビガトラン、リバーロキサバン、アピキサバン、エドキサバン、ワルファリンなどの薬が選択されます。
重篤な出血の合併症の発生率はダビガトラン、リバーロキサバン、アピキサバン、エドキサバンが少ないため、まずはこれらが用いられることが多いです。
血液を固まり難くすることにより脳梗塞の原因となる血栓や動脈の狭窄を防ぐ作用があります。
3.頸動脈内膜剥離術(CEA)
頸動脈に70%を超える狭窄がある場合は、抗血小板療法に加えCEAと呼ばれる頸動脈内膜を剥離する手術が行われる場合があります。
血管がどれくらい狭まっているかは頸動脈エコーや造影検査で分かります。
手術は全身麻酔下で頸部を切開し、頸動脈を露出させて行われます。
※頸動脈内膜剥離術=CEA(carotid endarterectomy)
4.頸動脈ステント留置術(CAS)
頸動脈に狭窄がありながら、CEAに対する危険性が高い場合に対し、ステントを留置するCASという手術を行う場合があります。
ステントとは金属の筒を動脈内に挿入し、動脈を広げ、血流を保つものです。
手術といっても、メスで切って行うものではなく、足の付け根の太い動脈から細いカテーテルを通して、頸動脈までカテーテルを挿入しそのままステントを留置する方法ですので、全身麻酔などの必要はありません。
※頸動脈ステント留置術=CAS(carotid artery stenting)
5.EC-ICバイパス術
内頸動脈および中大脳動脈閉塞、狭窄症の場合に、バイパス術を実施することがあります。
バイパス術は全身麻酔下で、閉塞または狭窄している部分の根元の血管と、閉塞より先の血管とを結んで問題の箇所を通らなくても末端まで血液が流れるようにする方法です。
※EC-IC(extracranial-intracranial)
急性期治療を行っても後遺症が残る場合がある
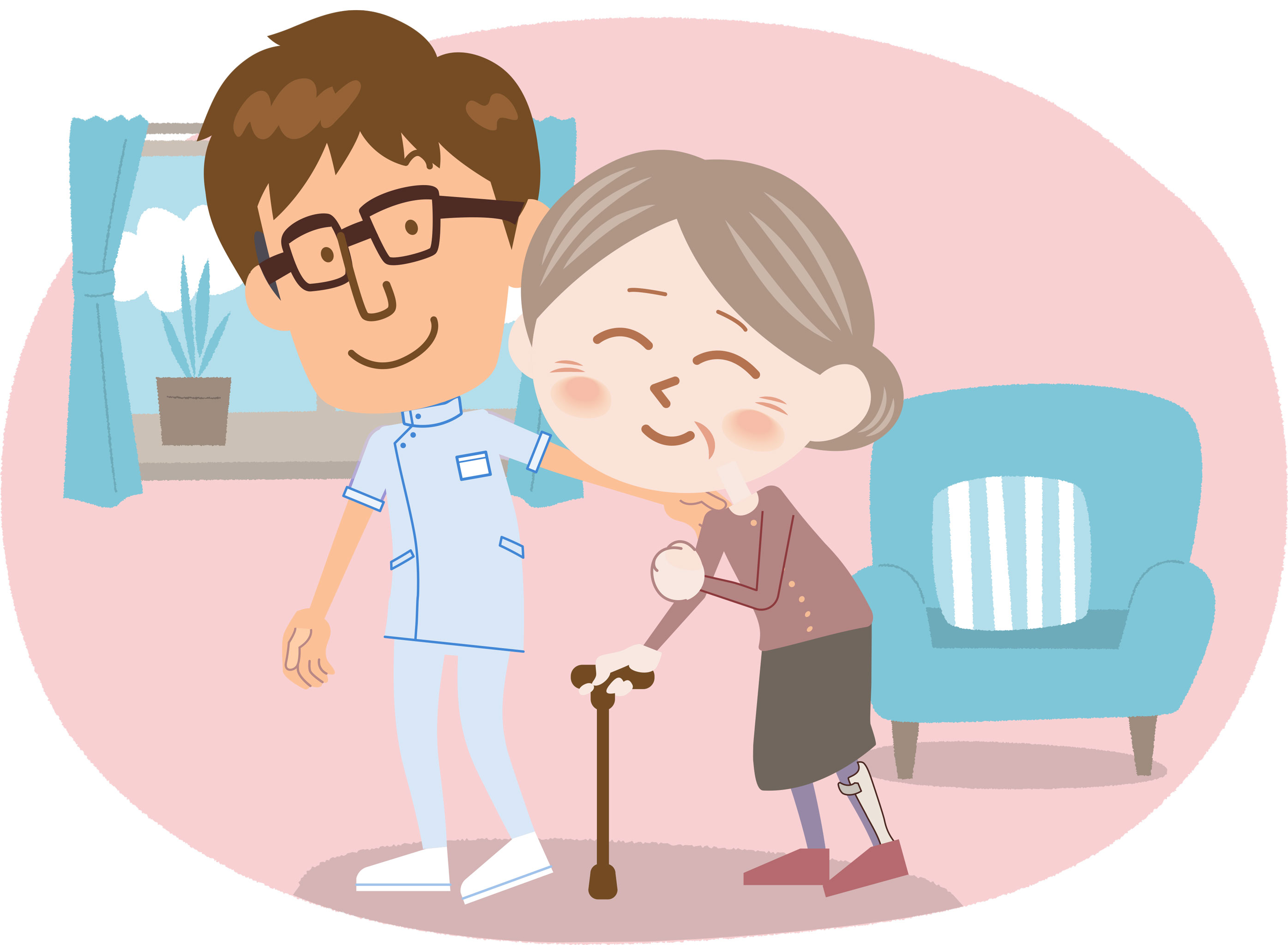
一旦死んでしまった脳細胞は再生しません。脳梗塞の急性期治療を行ったとしても、完全に機能が回復しない場合もあります。
どのような後遺症が残るかは、脳梗塞が起こった部位によって違いますが、主に以下のようなものがあります。
片麻痺(手、足)
右に脳梗塞が起こった時には、左側に麻痺が起こります。左の脳梗塞の場合は右側に麻痺が起こります。力が入らない、痺れる、感覚がないなどの障害が残ります。
嚥下障害
食べ物を飲み込む筋肉にも麻痺が起こり、飲み込む力が弱くなったりします。
言語障害
脳の言語を司る部分にダメージがある場合、言葉が出にくくなったり理解できなくなったりします。
精神症状
精神活動が低下し、うつ状態になったり、不安が強くなったり、感情がコントロールできなくなったりします。
リハビリ
脳梗塞に対するリハビリはその機能障害に合わせて、早期から開始されます。
まずはじめに、ベッド上でできるリハビリを開始します。
体の向きを変えたり、麻痺のある手や足を動かすことで、手足が固まることを防ぎます。
その後、寝返りや、ベッドサイドに座ったり立ったりする練習を開始します。
座れるようになれば、車いすに乗車し、移動を開始します。
立てるようになれば、歩行練習を開始します。
平行棒や手すりを使って立つ練習、立てれば歩く練習を繰り返します。病院の平行棒や手すりで歩けるようになれば、外で歩くために杖歩行の練習が始まります。
その他、食事や着替えなどの日常生活動作の練習を行います。
リハビリの期間は患者さんの障害の内容や程度によって異なります。
麻痺の軽い人はリハビリ専門病院に入院することなく退院する場合もありますが、麻痺が重く、退院しても日常生活に支障がある場合はリハビリ専門病院へ転院して更にリハビリを行います。
まとめ
脳梗塞の治療は一刻も早く開始することがその後の後遺症の程度に関係してきます。
運悪く後遺症が残ってしまった場合でも、早期のリハビリで元の状態近くまで回復させることも可能です。
また、脳梗塞が一度起こったということは、脳梗塞の再発リスクは高いということを意識して、その後の再発予防のための薬物治療の継続や生活習慣の改善をしていくようにしましょう。



