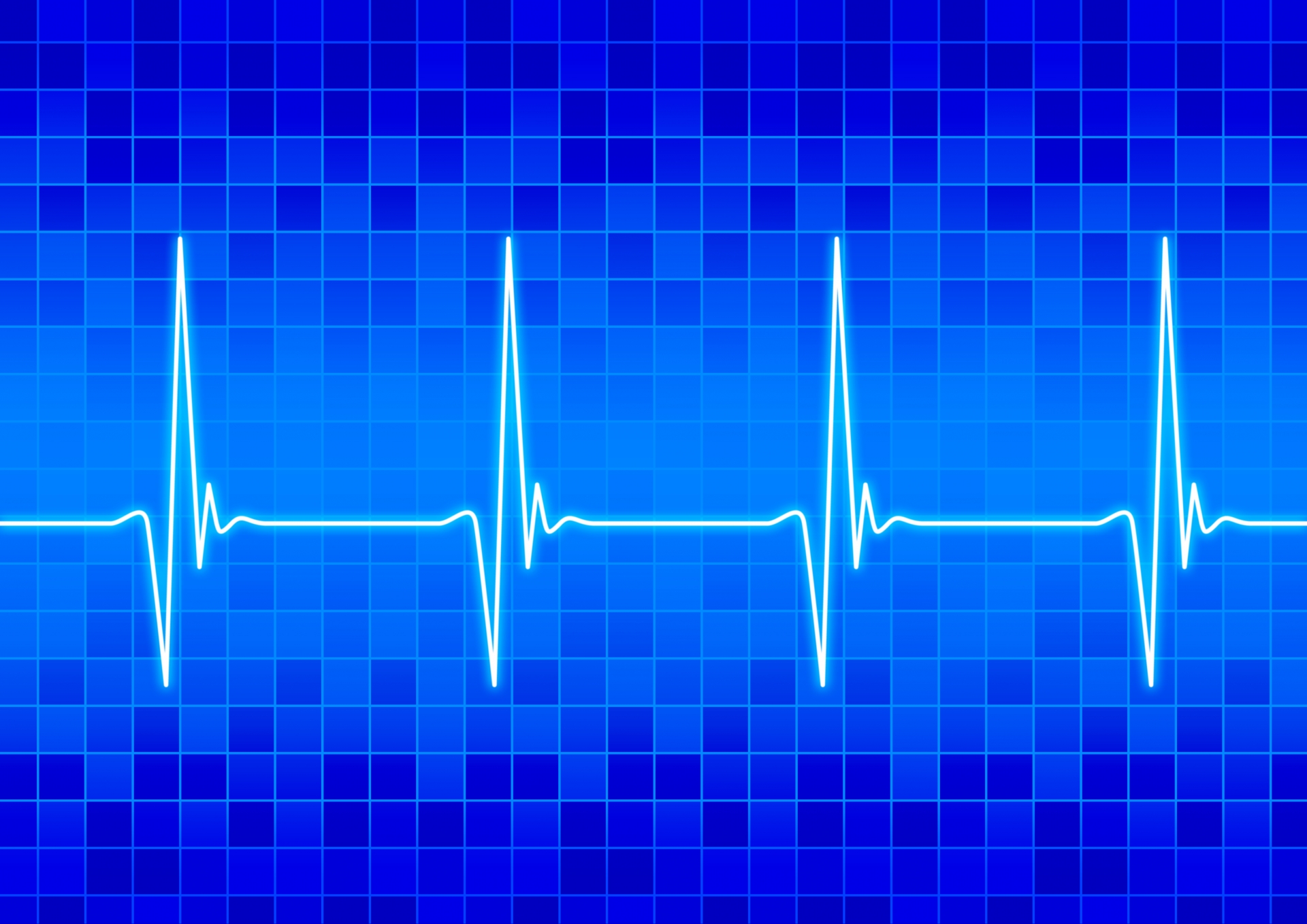不整脈の中でも、心房細動は比較的多くみられる不整脈です。
心房細動とはどういう状態なのでしょうか?
心房細動が起こる原因や心房細動の症状、また、必ず知っておきたい、心房細動と脳梗塞との関連を詳しく解説します。
不整脈って何?
心臓は全身に血液を送り出すポンプの役割があり、その動きは心臓内の電気的な興奮によって心臓が収縮する仕組みになっています。
この心臓の収縮は脈拍または心拍として、手首や頸の動脈が触れる場所や心臓に手を当てることで確認することができます。
この電気的な興奮を伝える経路(刺激伝導系)は、通常は規則正しく刺激を送り出していますが、何らかの異常で、不規則になったり、速すぎたり遅すぎたりする状態が不整脈です。
不整脈が起こるメカニズムに関しては、医師監修のこちらの記事「不整脈って何?原因とメカニズムに迫ります!」をご参照ください。
心房細動とは
不整脈には多くの種類があり、規則正しく打っていた脈が1拍だけ突然飛ぶものや、まったく規則性がなくバラバラに打つものもあります。
また、脈が乱れることで、全身の循環動態(各臓器へ酸素や栄養を含んだ血液が送られ、老廃物を排出する一連の働き)に異常をきたすものや、ほとんど影響のないものもあります。
心房細動は、本来の電気的な刺激の発生部分であるペースメーカー(洞房結節)から電気信号が生じず、心房内で不規則な電気信号が発生し、心房全体が小刻みに震えるようになる不整脈です。
心房細動は、ときどき起こる発作性心房細動と、心房細動の状態がずっと続く持続性(慢性)心房細動に分けられます。
初めのうちは数時間~数日以内(7日以内)の発作性心房細動を繰り返し、やがて発作の持続時間が長く(7日以上)なり(持続性心房細動)、やがて慢性心房細動に移行すると考えられています。
心房細動の原因

加齢
心房細動の原因の一つは加齢です。心房の筋肉の一種の老化現象と考えられており、年をとればとるほど起こりやすくなります。
特に60歳を境にその頻度は高くなり、80歳以上では約10人に1人は心房細動があると言われています。(国立循環器病研究センター 循環器情報サービスより)
高血圧やその他の病気
高血圧や心臓弁膜症、虚血性心疾患や拡張型心筋症などの心疾患によって心房細動が引き起こされることがあります。
また甲状腺機能亢進症(バセドウ病)も心房細動を合併しやすい病気です。
その他の原因
飲酒や喫煙、過労、ストレス、睡眠不足などが誘因となって心房細動を起こすことがあります。
若い人でも飲酒後の夜間に、一過性の心房細動を起こすことがあります。
心房細動の症状
心房細動を起こしている心臓は、心房は震えてしっかりと収縮していないため、心室に充分な血液を満たすことができず、全身に送り出す血液量も約20%減少します。
これにより、めまいや息切れ、動悸、胸苦しさ、失神などの症状を生じることがあり、これが続くことにより心不全になることがあります。
しかし、まったく症状がない場合も多く、心房細動が慢性化した高齢者では、その状態で循環動態が維持されているため、自覚症状がほとんどありません。
心房細動の問題は脳梗塞を引き起こすこと!
心房細動のみでは、命に関わることはありませんが、心房細動で最も問題となるのは、血栓による脳梗塞の発症です。
心房細動で心房が震えたような状態となると、心房の中に血液のよどみができ、血液が固まり血栓を作りやすくなります。
これがあると剥がれ、血流に乗ってほかの部位の血管を詰まらせてしまいます。
特に脳の血管を詰まらせることが多く、脳梗塞(心原性脳塞栓症)をひき起こします。
心房細動がある人は、ない人と比べると、脳梗塞を発症する確率が約5倍高いとも言われています。(国立循環器病研究センターより)
まとめ
心房細動は加齢に伴って起こる、よく見られる不整脈です。
症状のないままに長期間経過することもありますが、脳梗塞を発症するリスクがあり注意が必要な不整脈です。