今回のテーマは「鼻血」です。みなさんも一度は経験したことがあるのではないでしょうか?鼻血の原因や対処法、鼻血が止まらない時に気をつけるべき病気などについて詳しくお話しします。
ほとんどの鼻血は「キーゼルバッハ部」から出血!?気を付けるべき5つの行動
鼻出血の90%は、キーゼルバッハ部と呼ばれる鼻を左右に分けているしきり(鼻中隔)の前方から出ます(もう困らない救急・当直ver.2より)。これは、この部位が鼻の穴から近くて指が届きやすいことや、血管が網目状に多く集まり表面に浮き出ているため出血しやすいことが原因と考えられます。
普段の習慣や行動で、このキーゼルバッハ部を傷つける原因となるものを挙げてみました。
- 強く鼻をかんだり、思い切りくしゃみ・咳をする
- のぼせや興奮、刺激物を摂り過ぎる
- アレルギー鼻炎や風邪などにより鼻がつまる・かゆいなどの症状が出ているとき、鼻を強くこすったりする
- 鼻に指を入れたり、鼻をほじったりする
- ワーファリンなど血液をサラサラにする薬の服用
病気のせい!?鼻血の原因となる10個の病気
一次的な血圧上昇や触るなどして鼻の中が傷ついて鼻血が出た場合、そのほとんどはすぐに止血できるので問題ありません。しかし、病気や薬の影響で出血をした場合、出血を繰り返したり出血が止まらなくなったりすることがあります。
また、鼻血のほとんどの原因であるキーゼルバッハ部からの出血ではなく、鼻の奥からの出血をすると家庭での止血は困難なため注意が必要です。以下に、出血を起こしやすい薬や気をつけるべき病気を紹介します。
鼻の周辺の病気
上顎洞がん
上顎の歯の上側にある空洞を中心にがんが成長し、大きくなってくると鼻血や眼症状、歯の痛みなどをきたすようになります。通常片側からの鼻血がみられます。
上顎洞がんは、副鼻腔にできるがんのひとつで、耳鼻科での治療が必要な疾患です。副鼻腔にできるがんは、60~70歳台に多く、男性の患者さんが多い傾向にあります(がん・感染症センター 都立駒込病院より)。
血管腫
血管腫は、血管が異常に増えることでできる良性の腫瘍です。鼻にできる良性腫瘍の約半数を占めます。
出血しやすく、切除手術により治療します。
乳頭腫
鼻の粘膜の表面にある扁平上皮(へんぺいじょうひ)という組織が異常増殖することでできる腫瘍です。乳頭腫自体は良性の腫瘍ですが、再発しやすくがんと合併することもあります。
鼻血以外にも、鼻づまりなどの症状があります。
上咽頭がん
鼻から喉の上部までの空気の通り道のあたりを上咽頭と呼び、この位置にできるがんを上咽頭がんといいます。
鼻づまり・鼻血など鼻の症状と、聞こえづらさ・耳の閉塞感といった耳の症状、腫瘍のできる位置によっては視神経に影響して物が二重に見えるといった症状がでます。
なお、「風邪の症状かと思ったら…喉のがん、咽頭がんについて」の記事では、咽頭の図版や、咽頭がんに関する情報が紹介されています。
全身の病気
血友病
血友病は、血液凝固因子(血液を固めるタンパク質)が少ないために血液が固まりにくく、出血をした場合に止血しにくくなる病気です。
70%が遺伝によるもので、基本的には男性にのみ発症します(中四国エイズセンターより)。
白血病
白血病は、血球を作る細胞に異常が起こり、正常な血液を作ることができなくなる病気です。そのため、貧血や免疫力の低下、出血しやすい状態を引き起こしてしまいます。
70~74歳代で年間人口10万人あたり33.2人、80~84歳代では10万人あたり62.7人となり、高齢者の発生率が高い病気です。また、子どもは高齢者ほど発生率は高くないものの、小児がんの中に占める割合が高い病気です(JALSGより)。
ITP(特発性血小板減少性紫斑病)
ITP(特発性血小板減少性紫斑病)とは、原因は不明ですが、出血を止める血小板という物質が減少して出血をきたしやすくなる病気です。20~40歳台の女性と、60~80歳の男女に多いとされています(難病情報センターより)。鼻出血に加え、歯ぐきからの出血、四肢の皮下出血が見られます。
子供の場合は、ウイルス感染による風邪症状のあと2~3週間して急激に発症しますが、通常は6か月以内に自然に治ってしまいます。一方、成人の場合は明らかな誘因がなく徐々に発症し、良くなったり悪くなったりを繰り返します。自己免疫疾患と合併することも多い病気です。
肝炎肝硬変
肝炎はウイルス感染などにより肝臓が炎症を起こす病気で、慢性化することで肝硬変・肝がんなどのリスクが増加します。
また、肝硬変は、肝炎などにより肝臓の細胞が壊れ、肝臓が硬くなっていく病気です。肝臓の細胞が減少することで肝臓の機能が低下すると、黄疸、肝性脳症、歯茎からの出血や鼻血といった肝不全の症状が見られるようになります。
動脈硬化
動脈硬化は、加齢などにより動脈が硬くなる病気です。動脈の血液の流れが悪くなることで、全身に支障・弊害が発生します。
動脈硬化により弾力性が失われた血管は、脆く出血しやすくなります。
高血圧症
持続的に血圧が高いと、鼻の血管の圧力が高まって血管が脆くなり出血しやすくなります。
高血圧は鼻血だけでなく、心筋梗塞や脳卒中のリスクにもなるため、食事や運動、薬などによりコントロールすることが重要です。
正しい鼻血の対処法は?
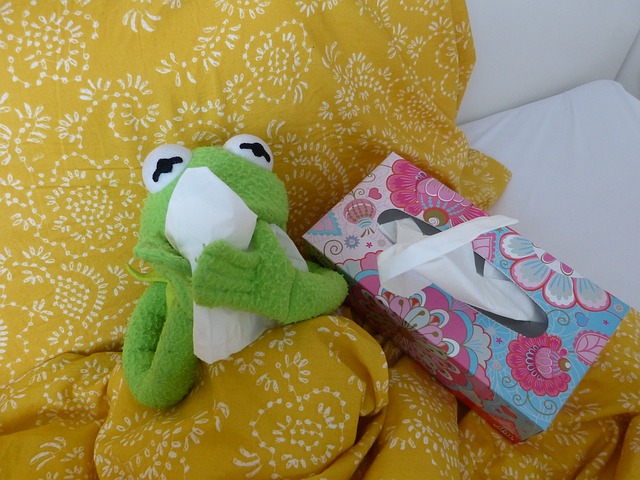
キーゼルバッハ部からの出血の場合、基本は家庭で簡単に止めることができます。指で鼻の両側をつまみ、10分間圧迫します。鼻をしっかり圧迫し、10分間は一度も手を離さないことが重要です。顔を下向きにして前かがみに座り、喉に入り込んだ血は飲みこまずに外に出すようにします。
この姿勢をとる理由は、出血している場所を心臓より高くすると止まりやすく、また顔を上向きにすると血が喉に流れて咳こんだり、飲みこんで気持ちが悪くなり吐いてしまったりすることがあるためです。
よく、後頭部をとんとん叩くといい、仰向けに寝るといいといわれますが、効果はないのでやめましょう。この方法で止まらない場合や鼻血を繰り返す場合は病院を受診するようにしましょう。
子どもは鼻血を出しやすい!慌てないで対応しよう!

子どもの鼻の粘膜や血管は大人に比べて未熟なため、ちょっとした刺激で簡単に出血してしまいます。さらに、体温調節も未熟なため、風邪などで熱が出ただけでも血管が拡張して鼻血を出してしまうことがあります。
大部分はキーゼルバッハ部からの出血なので、慌てずに前項で述べた対処法を実践しましょう。
ただし、鼻の怪我でどうしても止まらない場合や、鼻血に加えて全身の皮下出血、歯ぐきからの出血などがあり白血病などの血液疾患が疑われる場合は、すぐに病院を受診しましょう。
まとめ
鼻血はほとんどが家庭で治療できます。まずは落ち着いて正しい対処法を実践しましょう。
また、注意すべき鼻血については、いずれも鼻血以外の場所からの出血や、特徴的な症状があることがほとんどです。普通の鼻血とは違うと感じた場合には、耳鼻咽喉科を受診し、検査を受けましょう。
